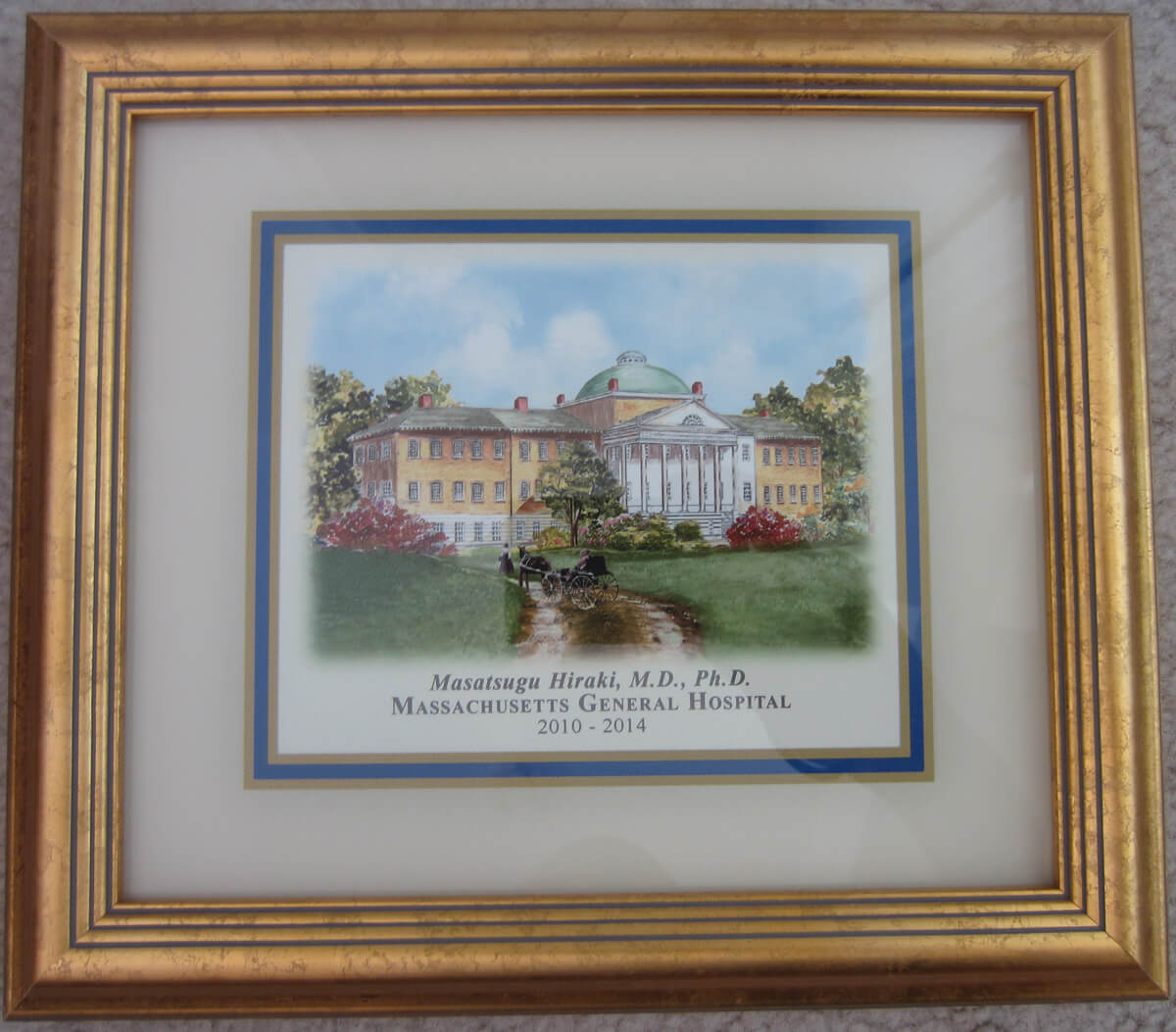留学報告記
平木 将紹 2014年
| 留学先 | 米国、 マサチューセッツ州、マサチューセッツ総合病院、ハーバード大学医学部 |
|---|---|
| 留学期間 | 2010年8月〜2014年9月 |
※この文章は2014年の佐賀大学 一般・消化器外科の同門会誌への寄稿文を一部改変した内容となっております。
みなさま御無沙汰しております。最後の留学便りになります。この便りを書いている8月末現在、本帰国 (9月末)のための船便の荷造りや諸手続き、そして先日アメリカで3度目の車の事故にあいまして(いずれも相手の過失ですが)バタバタしています。仕事の方はなんとか論文を8月1日に初回投稿ができまして査読結果を待っている状況で、難しいとは思われますがなんとか帰国までに追加実験を終わらせて帰れないかと画策しています。最後にこの留学生活を振り返って、最後の留学便りにしたいと思います。
この留学生活はかなり辛く長い道のりでした。まず始めにこのラボに来て初めて味わった日本との違和感。ラボに加わっても歓迎されるムードもなく、周囲は「また新しい人がきたな」程度の印象でした。もちろん歓迎会などありません。積極的に向こうから話しかけてくれる訳でもなく、そこから英語の話せない日本人が周囲とのコミュニケーションをとって、実験での信頼を勝ち得るにはかなりの時間を有しました。
仕事の方は先輩方のように2-3年で仕上げて帰国する事はできず、ここまで時間がかかってしまいました。 私が1から手がけたシステムが2回うまくいかず、3回目でなんとか突破口が開けましたが、投稿中の論文のfigure 1 をつくるために約2年を費やしました。その間他のメンバーと一緒に、ほとんど毎日のように「次のクビは自分かもしれない」と強迫観念にかられましたが、それはこのラボが持つ独特の雰囲気や歴史からでした。数ヶ月毎に回ってくるラボミーティングがきっかけで突然、解雇宣告を受けますので、ラボ内の雰囲気はいつも戦々恐々としていました。さらに、実験がうまくいってないメンバーは、極度の緊張のもとに望む年に1度の契約更新。これがきっかけで契約を更新されずラボを去った人も少なくありません。私が在籍した4年間のうち円満退職した人は3人だけです。しかしその3人はそれぞれNature, Nature Communications、Cell Reportsらの一流紙を出して製薬会社に就職が決まったり、他のラボにステップアップしたり、独立したポジションを得て異動していきました。このラボは世界のトップレベルにある施設に所属しますから、不自由ない研究機器、共同研究(思いもよらなかったbig nameとの仕事する機会も出てきます)、そして周囲には優秀な人材がそろっています。しかしそのラボ内での現実は非常に厳しいものです。一昨年の最高時にはメンバーが10名程いましたが、研究資金の先細りとともに人がどんどん人が解雇されていき現在5人のみ在籍しています。また、一番研究資金があったとき10名ほど面接を受けてその中から2人採用されましたが、その1人は3ヶ月で、もう1人は1年で解雇されました。私も何度も解雇されそうになりましたが、その都度なんとか修羅場を切り抜けてきました。
しかしながら、そのような厳しい環境の中で学ぶ事も多くありました。ボスからは「出るはずだ。お前の何かがおかしい」と言われ続け、手を替え、品を替え何十回と同じ実験をしました。そのうち、他の研究者に相談したり試薬の会社に聞いたりし色々な方法、実験道具、試薬があることを知り、そして手技も確立し確実に結果が出るほどになります。基本的にボスが親身になって一緒に考えてくれることはありません。「自分で考えて自分で切り開け!」です。私が日本で研究を始めた頃は数回やって出なければ終わりでしたが、それは自分の知識とテクニックのなさのために出ていない事も数多くあったと思います。それほど研究というのは奥深くかつ難しく、そして粘りを必要とするものだと気付かされました。
データが全くでない数週間の間、ボスから完全に無視・放置され、冷たい視線すら感じない事も数えきれない程ありました。投稿中の論文が気になりピリピリしている同僚からは、理由のない嫌がらせを受けた事もありました。私のプロジェクトでデータが出だした矢先、他の同僚がボスに進言して内緒で私の実験を始めていて、もめて大激論したこともあります。しかし、今となってはいい思い出や笑い話です。
では実際自分は成長したのか?よく疑問に思う事があります。知識、実験手技がなんとなくついたような気がしますが、元々研究の才能はない、アイデアが浮かばない、もちろん外科医としてはマイナス。ただ、この4年2ヶ月のアメリカ生活で非常に貴重な経験を得たのは間違いないと思っています。私の妻は渡米する前は自分で買い物すら出来ない、英語も話せないと言っていましたが、今では一人でどんどん英語を攻める姿勢がありますし、お店のレジで順番を抜かされると文句を言って撃退します。日本語も英語もしゃべれない状況で1歳の時に幼稚園に入れられた長女は既に5歳。なんとなく日本語と英語を使い分けられるようになり、さらには理解しているのか分かりませんがテレビでスペイン語の放送を見ていたりします。私も何かしら成長しているものと信じたいと思います。
これまで自分は井の中の蛙だとは認識していましたが、こちらにきて自分が想像していた大海とは水たまり程度のものであったことに気付きました。さらに蛙であると思っていた自分は、実はそれ以下の存在であるということも分かりました。それだけ世界には未知な事があり、自分の手の届かない人達が大勢います。こういうことが分かっただけでも大きな収穫ですし、間違いなくこのことを自分の子供達、若い世代には伝えられると思います。
癌研究には興味がありましたし一度世界の中に自分を置いてみたかった思いもありましたが、結果として外科医としては遠回りをしました。しかしこれも自分が選んだ人生。それを覚悟してアメリカに来た経緯もあります。これから自分の歩む道がどうなるか分かりませんが、また一つ一つ積み上げて行きたいと思います。